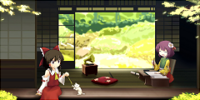テレビに上杉裕世さんというマットペインターの方が出ていた。様々なハリウッド映画で背景に使われる絵を描いている人だ。映画の中の非現実的な風景はCGで作られているように思われているが、実際のところ全てがCGというわけではなく、絵具で描かれた絵も随所に使われている。最終的に合成されて映画の中でその場面を見ると、まるで実写と区別がつかないから驚きだ。彼がアメリカで制作会社に採用される時のエピソードが面白い。学生時代に作った映像作品を見せたのだが、それは自作の特殊カメラを使い自分の絵を合成して原始時代のシーンを創り出した秀逸なものだった。それを見た面接担当者たちの言葉が”You’re crazy.”。最高の褒め言葉だったそうだ。▼「狂っている」と言われてしまうほど何かを追求できるということ。一流になる人とはそういう人なのだろう。
#005 夜空はなぜ暗い
夜空はなぜ暗いのだろう。唐突な疑問ではあるが、実は宇宙の成り立ちを考える上で重要な意味を持つ興味深い問いだ。この問いから、宇宙の有限性が導かれる。どういうことか。もし仮に宇宙が無限であるとすると、星もまた無限に存在することになる。遠くの星ほど光の強さは距離の2乗に反比例して弱まるが、一方で星の存在数は距離の2乗に比例して増大する。結果的に両者の効果は相殺され、無限の彼方からも近い所からと同じだけの光が届く。もし宇宙が無限であったなら、夜空は大量の光で満たされるはずだ。しかし実際には、夜空は暗い。ここから、宇宙の広さは有限だという結論が得られる。▼この話はオルバースのパラドクスと呼ばれ、さらに考えを進めれば宇宙の膨張やその起源にまで話は行き着く。夜空の暗さという当たり前の事実から壮大な宇宙論にまでつながる素敵な話だと思う。
#004 それでも飛んでいる
何かをを作り終わっていつも思うのは、自分がどうやってそれを作ったのか自分でもよくわからないということだ。手順はよく思い出せないけど、ともかく色々やっていたらいつの間にか出来ていたという感じである。例えば絵がそれだ。自分で描いたものであるにもかかわらず、どうやってそれを作り出したのかよくわからないし、同じものを再現できる自信がない。▼こうしたことはただ自分が未熟なだけだからだろうと思っていたが、案外世の中のモノというのは、どれもそのような感じなのかもしれない。飛行機がなぜ飛ぶのか、実はその理屈はまだ完全に解明されてはいない。一応理論はあるし、それを元に飛行機が発明されたが、のちにその理論は不正確であることが判明したのだ。にもかかわらず、現に飛行機は空を飛んでいる。そして、なぜそれが飛んでいるのか、正確には誰も知らないのだ。
#003 やる気
やる気というのは気まぐれなもので、ある時急にやる気が出たかと思えば、いつのまにか消えてなくなっていたりする。この切り替わりはどう生じるのだろう。自分の場合、やる気が出てそのまま行動につながるような事態は外発的な動機付けに起因する場合が多い。外的な評価や視線が具体的に予見できると、早くその期待に応えようと奮起する。内発的な動機付けも重要ではあるが、短期的な「勢い」を生じさせるのはやはり外的要因であることが多い。人は基本的に怠け者なので、ただ「興味がある」というだけではなかなか行動まで移らない。こうした意味で、やる気というのは社会的なものだ。▼だから、やる気が出ないときは人と話すのが良いのかもしれない。twitterで「やる気でない」というつぶやきをよく見かけるのも、みんなそのことを無意識的に知っているからではないかと思う。
#002 書くと描くの類似性
文章を推敲していて思った。この作業は、絵を描くときのそれと非常に似ている。句読点を付けたり外したりその位置を変えたりという一見些細な―しかしそれによって読みやすさが大きく左右されるような―文章の微修正作業というのは、絵を描くときに目の形や大きさ・位置を細かく調整して行く作業と、とてもよく似ている。絵、特にキャラクターイラストで最も重要な要素の一つは何かというと、それは目だ。髪のラインが数ピクセル変化したとしても絵に大した違いは出ないが、目のラインは1ピクセル変化しただけでも表情の違い、印象の違いとして知覚される。だから、ほんの小さな違いをめぐって延々とアイラインの微調整を行うことになるのだ。▼絵においてその印象を決定づける最も重要な要素が目であるなら、文章における「目」は何だろう。フォントや見出しがそれではないかと思う。
#001 吉里吉里人
作家の井上ひさし氏が亡くなった。『吉里吉里人』は強く印象に残っている。日本の東北のある小さな村が独立を宣言し、それを阻止しようとする日本政府との攻防を描いた小説だ。一見突飛なストーリーだが、それを可能とするための様々な策が具体的に示されていく。これならひょっとすると現実の日本で実際に遂行可能なのではないかと思えるようなリアリティがあり、小説というよりドキュメンタリィを見ている気分になる。▼登場する村人たちが身内同士であるいは外部の人と様々な議論や交渉をかわす際に東北弁を用いていたことが、妙に面白い。例えるなら新聞や教科書が方言で書かれているようなもので、その異化効果にグッとくる。この小説の面白さは、ストーリーもさることながら、村人たちの使う生きた言葉、日本語の奥深さであり、そこから示唆される国語論・方言論であったと思う。
サイトリニューアル
改装中
雪の道しるべ

雨 / Rainy Day
坂の上の雲 / Clouds over the slope
阿求
のどか / Peace
 こういう場所でゆっくりしたいものです
こういう場所でゆっくりしたいものです 鐘楼 / A Belfry
湖を一望できる場所
湖を一望できる場所 / Lake View
 幻想郷の果てまでよく見える!
これまで描いたものの中でも特に好きな一枚です。
幻想郷の果てまでよく見える!
これまで描いたものの中でも特に好きな一枚です。 ギターチルノ

フラン
時計塔
節分
雨道
回るパチュリー

パチュリー
夕日に染まる
 紅い空、紅い湖、紅い館。
差分イラスト?→■
紅い空、紅い湖、紅い館。
差分イラスト?→■ レミリア
雪のみちしるべ
 『雪のみちしるべ』という動画に使用された絵です。
レイアウトをキタノユースケさんが、彩色を私が担当しました。
竹林の朝の雰囲気をうまく出そうと頑張りました。
動画は http://www.nicovideo.jp/watch/sm9946205 で見れるのでよければ見て下さい。
『雪のみちしるべ』という動画に使用された絵です。
レイアウトをキタノユースケさんが、彩色を私が担当しました。
竹林の朝の雰囲気をうまく出そうと頑張りました。
動画は http://www.nicovideo.jp/watch/sm9946205 で見れるのでよければ見て下さい。